

協立総合病院は、日本神経学会准教育施設であり、レジデント修了後に日本神経学会認 定神経内科専門医の資格取得を目指す。なお、この取得には在職中に受験資格が出来る日本内科学会認定医を事前に取得しておく必要がある。当院の基本的な考 え方は、3年目で専門分野を固定するのは内科医のバックグラウンドとして不充分で、さらに幅広い経験をつんだ上で臓器別専門を深めるべき であると言うものである。そのために、少なくとも卒後3年目の1年間は、内科ローテート(循環器、呼吸器、消化器、腎、総合内科のうち3つ以上)を必須と している。
日本神経学会のミニマムリクアイアメントに基づく神経内科の専門研修は4年目から6 年目を想定しており、後期研修としては4年間のプログラムである。 成人学習理論に基づき、仕事を基盤に学習し、省察する実践家(reflective practitioner)としての臨床神経内科医の養成をめざして いる。
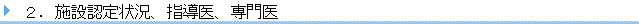
① 日本神経学会: 准教育施設
(神経学会のリンク
http://www.kktcs.co.jp/jsn-senmon/secure/sisetsu.aspx )
② 指導管理責任者名 : 田中 久
③ 指導医名 : 田中 久
④ 専門医名 : 田中 久 小池春樹(非常勤) 藤岡祐介(非常勤) 古池 保雄(非常勤)
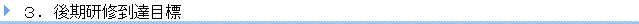
後期研修では以下の内容を身につけ、研修終了後には神経内科専門医取得可能となる。
- 1.ミニマムリクアイアメントで定めた神経学的症候や病態の意味を正しく理解 し、 適切な神経学的所見をとることが出来る。
- 2.神経生理、神経放射線、神経超音波、神経病理、神経遺伝学をはじめ、各種 神 経学的検査結果の意味・解釈や治療の内容を理解出来る。またミニマムリク アイアメントで定めた検査、治療、手技は自ら施行し、適切な判断を下すことが出来る。
- 3.適切な確定診断を行い、治療計画を立案し適切な診療録を作製できる。ミニ マ ムリクアイアメントで定めた疾患については主治医として十分な診療経験を 有している。
- 4.診断・治療方針の決定困難な症例や神経内科救急をはじめ迅速な対応が必要 な 症例 などにおいて、自科の専門医、他科の医師に適切にコンサルトを行 い、適切な対応ができる。
- 5.コメディカルと協調、協力する重要性を認識し、適切なチーム医療を実践で き る。
- 6.患者から学ぶ姿勢を持ち、患者と患者の周囲の者に対するメンタルケアの大 切 さを知り、実践できる。
- 7.神経学的障害をもった患者の介護・管理上の要点を理解し、在宅医療を含め た 社会復帰の計画を立案し、必要な書類を記載出来る。
- 8.神経内科救急疾患における診察の仕方、処置の仕方について学び、実践でき る。
- 9.医療安全、倫理、個人情報保護の概念、医療経済について必要な知識を有す る。
- 10.カリキュラムの修得度を定期的に自己評価するとともに、指導医の評価も 受 け つつ、自己研鑽を積み重ねる。
- 11.ミニマムリクアイアメントは、全項目中80%以上においてAもしくはB を 満 たす研修を積むことが出来るよう、自施設における習得が不十分な内容は、神経学会をはじめ関連学会の主催する教育講演、生涯教育講演、ハンズオンセミ ナーな どに積極的に出席し、学習する。
| 1年目(卒後3年目) |
|
循環器、呼吸器、消化器、腎、糖尿病、総合内科のうち3科目以上を、少 なくともそれぞれ3ヶ月以上ローテート 研修する。指導医・上級医による指導をうけながら、主治医として外来・入院診療の研鑽を積む。また神経内科症例検討会にも出席し、神経内科の考え方や知識 を学び、必要な診断方法や治療方針を習得していく。 また、主治医ではなくとも、カンファレンスや総回診を通じて幅広い疾患 に対する理解と経験を深める。内科の検査業務につい ては、指導の下に適切に施行出来 るようにする。救急外来では、内科救急全般に対する処置について研鑚を積む。 外来では、退院後の患者の治療継続を行い、疾患の縦断像を把握出来るよ う努める。指導医や上級医の指導の下、各種書類を適 切に記載する。医療安全・医療倫 理の講演会には積極的に出席する。また屋根瓦の一部として、初期研修医のプリセプターの役割を果たす。 |
| 2年目(卒後4年目) |
|
指導医・上級医による指導をうけながら、主治医として外来・入院診療の 研鑽を積む。神経内科症例検討会を通じ て神経内科の考え方や知識を学び、必要な診断方法や治療方針を習得していく。 また、主治医ではなくとも、カンファレンスや総回診を通じて幅広い疾患 に対する理解と経験を深める。検査業務については、 指導の下に適切に施行出来るよう にする。救急外来では、神経内科救急に対する処置について研鑚を積む。外来では、新患の診察と退院後の患者の治療継続を行い、疾患の縦断像を把握出来るよ う努める。指導医や上級医の指導の下、各種書類を適切に記載する。 医療安全・医療倫理の講演会には積極的に出席する。希望があれば、前年 に回りきれなかった内科ローテートを行ってもよい。 内科認定医試験を受け、認定医の 取得を目指す。初期研修医のプリセプターの役割も引き続き担う。 |
| 3年目(卒後5年目) |
|
引き続き、指導医・上級医による指導をうけながら、主治医として外来・ 入院診療の研鑽を積む。神経内科症例検 討会を通じて神経内科の考え方や知識を深め、診断方法や治療方針を習熟していく。カンファレンスや総回診を通じて幅広い疾患に対する理解と経験をさらに深 める。基本的な疾患では適宜指導医・上級医に相談しながら一人で診療可能なレベル到達を目指す。検査業務についても基本的な内容は一人で施行出来ることを 目標とする。 救急外来では、神経内科救急に対する経験を深める。積極的に外来業務を 行い、疾患の幅広い知識を身につけるとともに、引き 続き疾患の縦断像を把握出来るよ う努める。指導医や上級医の指導の下、各種書類を適切に記載する。 医療安全・医療倫理の講演会には積極的に出席する。 |
| 4年目(卒後6年目) |
|
主治医として外来・入院患者を受け持ちながら各種検査を行うとともに、 臨床研修医の上級医としての指導も行な う。教育関連病院との連携を通じて在宅の状況を把握出来るように努め、全人的な診療の中での神経内科診療の習得を目指す。 神経学会の定めるミニマムリクアイアメントを適切に達成出来るよう、指 導医と相談し、不足する研修内容は関連病院、学会ハ ンズオンセミナー、各種学習会な どを通じて習得出来るよう研鑽に励む。 神経学会専門医試験の受験を目指す。 |
検査業務
脳波・電気 生理、頚部超音波検査、高次脳機能検査、自律神経検査、その他希望に応じ て神経放射線検査、嚥下造影など。
カンファレンス
新入院症例 提示、症例検討会、放射線読影会、総回診、リハ ビリテーション・放射線カンファレンス、CPC、抄読 会、連携病院との検討会など。
研修記録と修了評価
1) 神経 内 科専門医を目指す研修医は神経学会のホー ムページにあるミニマムリクアイアメントをダウンロードし、3年間で全ての項目の研修が出来るう目標を定める。
2) 指導 医 は、年度毎にミニマムリクアイアメント達 成状況を確認し、過不足なく研修が出来るよう努める。
3) 3年 間 の研修修了時、もしくは自施設を研修医が移動する際に、指導医は神経学会 のホームページより研修 修了証明書をダウンロードし、必要事項を記載の上、研修医に渡す。
4) 評価 記 録の記載されたミニマムリクアイアメントと研修修了証明書は神経内科専門 医を受験する際に必要となる可能性があるので、研修医と指導医は大切に 保管 すること。
※ このスケジュール は例であり、各施設に応じて十分な研修が出来るよう工夫する。
※ 後期研修の途中に 他の教育施設、准教育施設、教育関連施設から移動してきた研修医に対し、指導医は前施設におけるミニマムリクアイアメントの到達度を把握して、個別のカリ キュラムを作成することが望ましい。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 外来 | 超音波検査 生理検査 |
抄読会 病棟回診 |
外来 | 教育回診 生理検査 |
| 午後 | 病棟回診 | 病棟回診 症例検討会 |
放射線検査 読影会 リハビリカンファレンス |
生理検査 病棟回診 |
病棟回診 新入院症例カンファレンス |